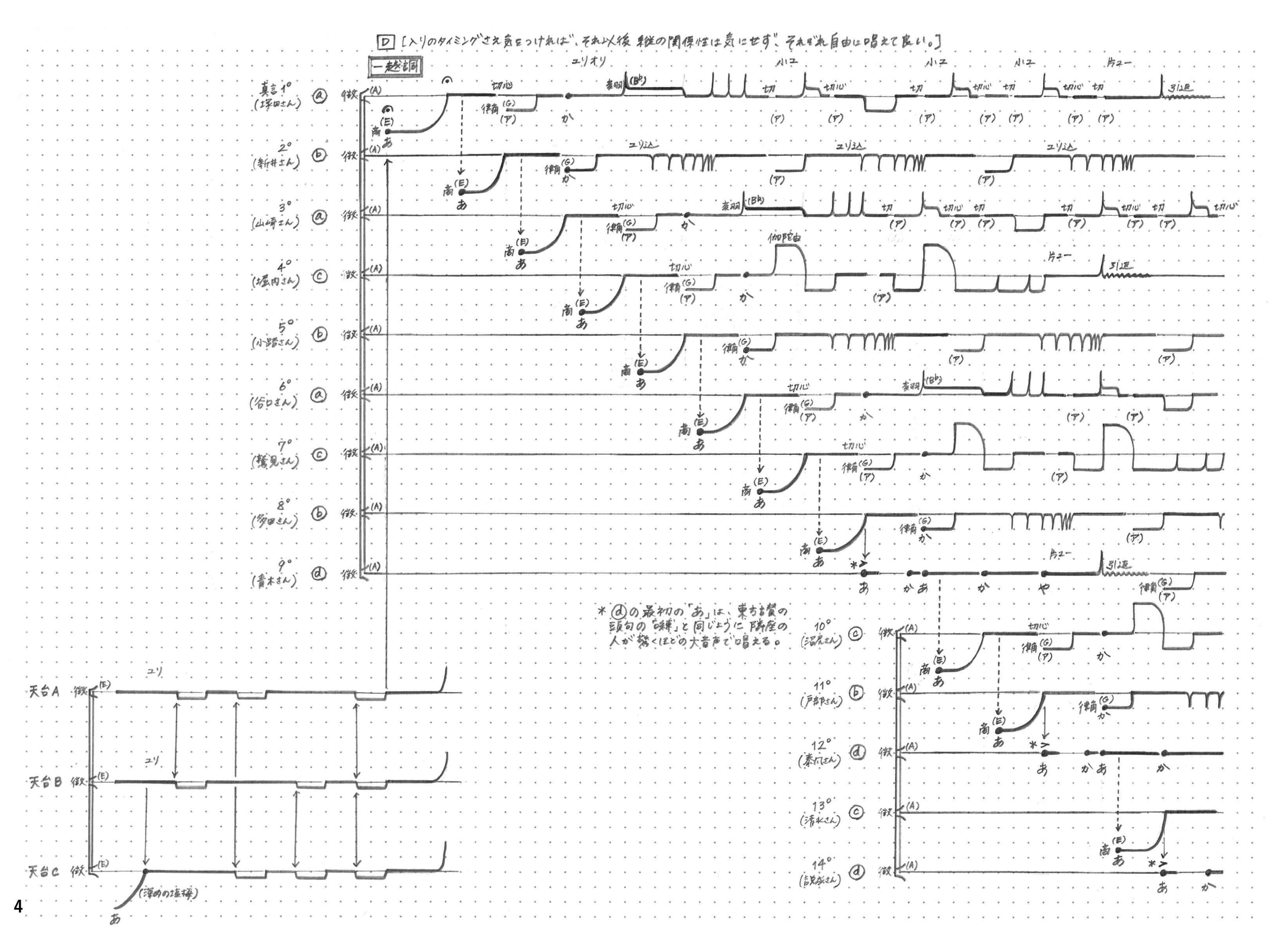クラシック音楽との出会い
———まず、桑原さんがどういうきっかけで作曲を始められたのか、そのルーツについて伺えればと思います。(小島)
桑原ゆうさん(以下、桑原): 3歳から音楽教室に通ってグループレッスンを受けていたんですが、当時の先生が「なんでも自分でやりなさい」という方針の面白い方で、伴奏とか変奏とかどんどんやらせてくれました。それで、小学校一年生の時に「曲を書いてみよう」となり、《きりんのおさんぽ》という曲を書いたのが最初です。その後も、なにか遊びで弾いたり、いろいろ自分で工夫して作ってみせたりすると「面白い」とびっくりされたり、褒められたり、喜んでもらえたりして。それが嬉しかったので作曲を続けてました。本格的にクラシックに興味を持って「作曲家になろう」と思ったのは中学生の頃ですね。小学生の時にも、本を読むのが好きだったので、物語を音楽にしようみたいなことはしてたんですが「クラシックってよくわかんないな…」っていう感じでした。最初に関心を持ったのはドビュッシーやラヴェルの曲です。とくに好きだったのはラヴェルで、そのオーケストレーションに惹かれました。
———その後、高校は音楽科ではなく普通科に進まれたんですか?(小島)
桑原:中学二年生から作曲の先生についてましたが、その方に「高校は音楽高校よりも普通高校に通って、作曲家としてというよりは人として、いろいろと経験を積みなさい」とアドバイスされました。それと、私は勉強が好きだったんですよね、小さい頃から。自分で学ぶこと、わかることが楽しいし、勉強の仕方を工夫するのも楽しかった。それで千葉県の進学校に進みました。
———進学校だから、一般の大学に進学する生徒が大半だったと想像します。みんながテストの勉強をしてる横で桑原さんは東京藝大に入るための勉強をする、みたいな状況だったのでしょうか。(小島)
桑原:そうですね、数学の授業のときにバッハの楽譜とかを広げていて、怒られた記憶があります(笑)。周囲がいろんな方向で頑張っている人たちだったので、それが良かったですね。今でも同級生がそれぞれの分野で活躍していて私も励みになるし。とくに作曲はそうだと思うんですけど、音楽って音楽だけでは考えられないところがありますよね。多角的、多面的、多元的に物事を見られないといけない。その点でも普通の高校に通ったことはよかったです。
———普通の進学校に通って、それぞれが別々の分野で頑張っているという環境が今でも活きているわけですね。
中学生のときにドビュッシーやラヴェルからクラシックの世界に入り、高校生になると大学受験に向けて専門的な勉強をされ、世界も広がったのかなと思うのですが、その頃の桑原さんの作品や作風はどういうものでしたか?(小島)
桑原:私は小さい頃にピアノを始めたんですが、小学四年生くらいでエレクトーンをメインの楽器に選んでいて、その頃からエレクトーンで音楽を考えています。つまり、ピアノの音色ではなく、まずオーケストラで発想するんです。ラヴェルやドビュッシーの楽曲もエレクトーンで弾いてました。少し進んだ時代のディティユーとかメシアンも好きになったので、そういうフランス系の作曲家に影響を受けて書いた自作をエレクトーンで弾いたりもしていました。コンクールに出て、全国大会で金賞をとったりもしたんですよ。
その後、高校一年生のときにエレクトーンはいったんやめて、完全に作曲の方にシフトしました。その頃から、もっと幅広く現代音楽を聴き始め、古典の音楽もちゃんと勉強するようになりましたね。当時、好きだった作曲家はブラームスで、彼のような曲を書いていたと思います。
———それは受験のときくらい?(小島)
桑原:そうですね。受験生のときは毎週曲を書いて先生に持っていきましたが、後で「君はブラームスみたいな曲を書いてたよね」って言われました。
———「現代音楽」の作曲家でいうと武満徹やクセナキスなんかもブラームスに関心を持っていたようですが、桑原さんはどういうところに惹かれたんでしょうか?(原)
桑原:その頃はブラームスの転調の仕方にすごく憧れたんですよね。ころころ転調するじゃないですか。あれにすごく惹かれて、自分でもできるようになりたいなと思いました。それと、対位法やリズムの面白さもあるし、すべての点でこうにしかならない、これが最も正しいと、納得させられるものがありました。それでいて、人にストレートに訴えかけるものがあるのがいいなと当時は思っていました。とくに好きだったのは《ピアノ三重奏曲第一番》でしたね。
———古典の勉強をしなきゃというよりも、ブラームスに魅せられたというような?(小島)
桑原:「勉強しなきゃ」っていうのは常にありますよ。ただ、「大学に入るために」というのはあんまり頭にありませんでした。藝大の入試では、三次試験に冒頭の動機と楽器編成指定の自由作曲がありますが、それも全然型など決めずに挑み、ただ八時間作曲して帰ってきました。リハーサルはしましたけどね。いわゆる受験的な作曲はしたくなくて、ちゃんと自分の曲を書いて帰りたかったんです。
音になりたがっているもの
———藝大に入った後もブラームスを参考にしたのでしょうか。モデルや理想とするものが他の作曲家にあったとしたら誰でしょうか?(小島)
桑原:私は「現代音楽」ないしはその先の芸術音楽を書きたくて、大学に入ったらそれをばりばり書くぞって決めてました。メシアンにも影響を受けましたが、私の先生は「シェーンベルクを勉強しなさい」という方だったのでシェーンベルクやベルク、ヴェーベルンあたりはすごく勉強しましたね。あとはバルトークとか。先ほど名前が出たクセナキスは今でも最も好きな作曲家のひとりで、早くから聴いていました。
———大学で作曲された作品は聴くことはできないんでしょうか?(小島)
桑原:大学に入った一作目は木管五重奏曲でしたが、2019年に個展をやったとき、一曲目にそれを演奏しました。なので、音源はあるといえばありますね。明らかにシェーンベルクから影響を受けた作品で、内容もまだまだではありますが、いま振り返っても「頑張って書いていたな」とは思います。当時それを音にしてくれたのは、大学二年生の木管五重奏の方々で、今でも「アンサンブル・ミクスト」として活躍されています。個展の時にもお願いして、演奏してもらいました。
———大学生の頃、たとえば周囲の学生と比べて、桑原さんの特質はどういうところにあったと思われますか?(小島)
桑原:今から振り返ると、私は構成する力がすごく弱かったように思います。ただ書きたい音のイメージはすごく強かった。音の発想の仕方は周りの学生とはちょっと違っていて、それはエレクトーンをやっていたことが関係してるのかなと思いますね。同級生の多くはピアノをベースに考えて、それをオーケストレーションしていくという仕方で室内楽やオーケストラの曲も書いてたと思うんですけど、私の場合は音のイメージが最初からオーケストレーションされた状態で浮かぶので、そこが違ったような気がします。
———大学の課題では、編成がオーケストラということは稀で、小編成の課題が多いと思うんですけど、そういうときにはオーケストラで浮かんだ音のイメージを割り引いたりするんですか?(小島)
桑原:そういうことではなく、たとえば、ピアノとなにかのデュオだったら初めからデュオのかたちで、あわさった状態での音のイメージが頭のなかに浮かぶということです。その全体の音のイメージを細分化していくと楽譜になる。このイメージを実現するために、どうやって楽譜に書いたらいいかなっていう作業になります。
———全体というのは、はじめから楽曲の全体がぼんやりと浮かび上がってくるということですか?(小島)
桑原:いや、楽曲の全体ではなく、その要素となる音のイヴェントのひとつの像みたいな感じですかね。もっと短いスパンです。
———そこからどんどん広がって楽曲ができるという感じですね。今おっしゃった音のイメージのようなものが、スタイル&アイデアに寄稿していただいた論考でいう「音像」にあたるものですか?(小島)
桑原:そうですね…いま説明したことも「音像」に含まれるんですが、それは既にデベロップしたあとの「音像」で、音や音響に近いレベルの状態です。そのもっと手前の原始的な部分もあります。「音像」にもいくつかレベルがあると思ってください。
———音以前のもっと根源的な部分というような?(小島)
桑原:そうです。まだ音になりきっていない、音になりたがっている、ただのエネルギーの発露みたいなものも、今のところは「音像」と捉えています。もしかしたら、それにもちゃんと名前を付けなければいけないのかもしれないですけど。とにかく、エネルギーから音になるまでの過程にいくつかレベルがあるんですよ。
———先ほど、構成する力が不足していたとおっしゃっていましたが、その後、形式感をしっかりしていく方向に進むというよりは、むしろ、そうした響きの面白さや音のイメージの表現を伸ばすことを意識されたんでしょうか?(小島)
桑原:当時は自分で構成が弱いことに気づいていなかったんですよね。なので、音の面白さの方にどうしてもフォーカスしていたかなと思います。
大学生の頃は本当に思いつくがままに書いていて、それを客観視する力もあんまりなかった。大学二年生の終わりで室内楽、三年生でオケの曲を提出しないといけなかったんですけど、室内楽の曲はカオスですよ。書きたい音を全部書いているから譜面は真っ黒。オケの曲は、オーボエとトロンボーンのダブルコンチェルトを書いたんですが、それも真っ黒です。この編成は、その時は面白い組み合わせだなと思ったのに、武満に《ジェモー》という同じ編成の曲があると知ってがっかりしました。そういうのも懐かしい思い出です。
室内楽もオケの曲も、日本音楽コンクールの本選に二年連続で残ったんですが「演奏不可能」「全然演奏できない」って言われ続けて、リハーサルでは悔しくて泣きましたね。
———桑原さんは当時まだ大学生で、その作品をプロが演奏してくれるという構図になるかと思うんですが、プロに「このパッセージは弾けないよ」って言われたら、作曲家としてはどうするんですか?(小島)
桑原:なんでもいいからとにかくなにか言う、なるべくその場で対応するのがいいと思いますが、そのときは、はじめてだったのでそうした対応も全然。ただ泣くばかりでした。パーカッションのパートも一人で演奏してもらう想定だったのに「こんなの一人でできない」って言われて、もう一人増やされたりとか。あとでその曲がシュトゥットガルトのアカデミーで演奏されたのですが、打楽器奏者は一人で演奏可能でしたけどね(笑)。そういったリハーサルの経験も、今になって色々と活きてるなと思います。
———それ以前も自分の作品が音になる機会はあったと思うんですけど、はじめてプロによって演奏される機会があったとき、自分のイメージしていた音が実際に鳴りましたか? (小島)
桑原:全然でしたね、とくにオーケストラ作品は。会場がよく響くところだったので、打楽器と金管で埋め尽くされてしまって、思ったように聴こえなかったのを覚えています。思い通りにいった部分といかなかった部分があって、その割合は経験を重ね、耳のなかに音のサンプルのようなものが増えていくにつれて、前者が少しずつ増えていきました。
———経験を積むうちに、思った音が鳴る譜面が書けるようになったということですか?(小島)
桑原:そうですね。経験から学んで、楽譜の書き方などをどんどん工夫していきました。リハーサルでのやりとりも、だんだんスムーズになっていくし。リハーサルの経験は作曲家にとってすごく大事だと思いますよ。
音像、身体、空間
———大学生の時に、既に成果を残されていたと思うんですけど、大学院に進むときに悩みや葛藤はなかったんですか?(小島)
桑原:なにも決めてなかったというか、むしろ二年間の猶予が欲しかったですね。それで、とりあえず大学院に進みました。
———論考によれば、その大学院で日本の音楽に出会った。これが今の桑原さんにとっては大きな出来事だったかと思うのですが、この辺りの経緯を詳しく聞かせていただけますか?能について学ぶ機会を得たのは、大学院のクラスですか?(小島)
桑原:いいえ。それは誘ってもらって参加した外部のワークショップで、です。同世代の五人の作曲家が集まったんですが、いまでもみんな活躍しています。
大学二年生くらいから「とにかく大学の外に出なきゃ」という思いが強くなったんですね。なにか外に機会があればそれに参加して、コンサートや映画もその頃に一番足を運んでましたね。コンクールに作品を出してみたのもそういう理由です。
———そのワークショップは、能のエッセンスを取り入れた現代音楽をみんなで書くといったような?(小島)
桑原:「謡(うたい)」を扱うことが条件でしたね。
———桑原さんも最初はうまくいかなかったと論考で書かれていましたね。誰にとってもなかなか難しいのかなと思うんですけど。(小島)
桑原:作曲する以前に、謡を半年かけて習ったのですが、私が一番謡えなかったと思います。素直に真似すればいいのに、それすらできなかったんです。「なんでこうなるんだろう?」って思う気持ちが強かったのか。
———そこで「能は自分には合わない」と考えるのではなくて、なんとか取り入れようと苦心されたわけですか。あるいは自然に馴染んでいったんですか?(小島)
桑原:勉強しましたね。先ほども言ったように、もともと勉強が好きというのはありますが、私はすごく負けず嫌いなので、自分にわからないものがあるのが嫌でした。お恥ずかしいんですけど、当時は若かったので。
———私のイメージですが、西洋伝統現代音楽的な創作よりも日本のエッセンスに着目した創作の方が、音像を掘り下げるような作曲に合うのかなと思います。やはり日本の音楽に出会ってから、音像を掘り下げる行為としての作曲というアイデアも顕在化していったと理解してもよろしいでしょうか。(小島)
桑原:おそらく最初からそれがやりたかったんですよね。でも、自分で自分が何をしているのか、何がしたいかがわかっていなくて、具体化や言語化が全然できていなかった。言語化は今でもまだ不十分ですけど。とにかく「謡(うたい)」に触れたときに、「こういう風にエネルギーを扱う方法もあって、私がやりたかったのはこれだったんだ」ということに気づいたんです。
もともと私は音を引っ張ったり、グニャって曲げたり、音が質量を持っていて、そこに圧力をグーってかけていったら、そこから飛び出たものが音になる、といったようなイメージを最初から持っていたんです。そういう音を書こうとはしていたんですけど、それを客観視できていなかった。そういう音を扱う仕方を能楽に発見したということです。
———それが大学院の一年生の時ですよね。それ以来、一貫して、日本のエッセンスを取り入れた創作に取り組まれている。(小島)
桑原:一貫してかどうかはわからないんですが、軸としてはあります。「これをやらなきゃいけないんだな」っていう使命感みたいなものを感じました。
———さきほどのお話からすると、音像というのは押し出して弾け飛ぶといったような、視覚的なイメージを持つ場合もあるのですか?(小島)
桑原:視覚、なのかな…視覚ももちろん含まれますが、もっと身体的で体感的なものだと思っています。触感も含まれるし。舞の動きのように、音にも伸び縮みがあって、それが私の身体ともリンクしていて、音が空間内に広がったり縮まったりするときに、私の身体も会場内に広がっていくような、そういう感覚があります。「私にとって音ってそういうものなのかな」ってことに気付いたんです。
———そういった音とリンクした身体感覚は前々からずっとあったのでしょうか。子どもの頃から、そういう音の感じ方をされていたんですか?(原)
桑原:いや、子どもの頃は、さすがになかったと思います。
———とすると、どこかの時点から、そういう感覚が段々と意識されてきた?(原)
桑原:はっきりとは覚えてないんですが、高校生の頃から少しずつ自分で現代曲を演奏していくなかで、そういう身体感覚がちょっとずつ付いてきたような気がします。エネルギーが目の前をかすめてパッと過ぎ去っていく感じとか、摩擦や抵抗を感じながらゆっくり押し進めていく感じとか。ダイナミクスやテンポ、リズムだけでは表現できないものが音にはあるということが少しずつわかってきたというか。
———先ほどから名前が出ているクセナキスにしてもそうですが、空間性は「現代音楽」において非常に重要ですよね。そういう作品に触れるなかで、音と身体感覚、空間的広がりといったものが次第に結びついていった、あるいはもともと持っていたものが開花していったというのは納得です。(原)
桑原:そうだと思います。そうした結びつきの感覚が、日本のものをみることによって、ぐっと身近になった感覚があります。
———桑原さんの音楽はラヴェルに比べたら「現代音楽」だし、いわゆる西洋音楽よりも日本の音楽だなという印象があるので、次第に興味関心が広がっていったというよりも、段々視野が広がるうちに自分にあうものや、自分の表現ができる方法が見つかったという風に捉えられるかもしれませんね。(小島)
桑原:そうかもしれないです。
楽譜のフォーマット
———大学三年生のときのオーケストラ作品のように、学生時代には細かく音符を埋めた真っ黒な譜面を書かれていたということでしたが、現在の桑原さんの楽譜をみるとむしろ余白に満ちているというか、「あそび」の部分があるようにも思います。演奏における余白みたいなものについてどのようなお考えを持たれているかをうかがいたいです。(小島)
桑原:その余白というのはどういった意味ですか?偶然的なもの、演奏家の解釈的なこと?
———論考のなかで、桑原さんの楽譜には細かい揺らぎや抑揚、微妙な間合いなどが詳細に書き込まれていて、それを再現してもらえれば、桑原さんが感じている身体感覚や音のイメージが再現できるんだ、そういう風に楽譜を書いているんだ、とあったかと思います。作曲家のなかには、たとえ可能な限り細かく書いている場合でも、演奏時に不確定的な揺らぎが出てくることをむしろ歓迎する人もいるわけですが、そのあたりのお考えをお話いただけますか?(原)
桑原:楽譜に絶対に書けないものもたくさんありますよね。先ほど言った通り、ダイナミクスやアーティキュレーション、テンポ、リズムの音価などだけでは表せないものが本当にたくさんある。なので、もちろん楽譜から抜け落ちている部分というのはあります。それは充分承知のうえで、私にとって「これだけは絶対にやってほしい」ことは全部書いているということです。論考では「全部書いてある」って言ってますが、これはけっこう啖呵を切ってます(笑)。でも、そのくらいの姿勢じゃないと駄目だと思っていますね。「ここにとりあえず全部書いてあるから、まずはこれをやってください」っていうのが基本的な姿勢です。その上で、演奏者それぞれの解釈があれば、それを取り入れてもらっても構いません。
この「楽譜に書ける部分と書けない部分」をどう考えるかが、作曲家それぞれの様式を決めるし、そこを判断するのが作曲だと思います。私も、曲によって両者のバランスは変えたりしていますよ。「ここは絶対やってほしい何%で、余白は何%」みたいな感じで。「この曲はこのバランスだな」みたいな。
———たとえば、声明に対して書くのと、西洋的な器楽に対し五線譜で書くのとで、そのバランスの取り方に傾向はありますか?器楽の方は「絶対やって欲しい率100%」に近い感じで、とか。もちろん曲によるかとは思いますが。(原)
桑原:おっしゃる通りで、器楽はほぼ100%のことが多いですね。楽譜のフォーマットの選択と私の思うバランスは関係してると思います。たとえば、朗読が入る場合には100%にするわけにはいかないですし、たとえば箏の曲を縦譜で書いたときにも、それは絶対100%にはならないですよね。
———記譜の選択については、論考にも書かれていましたね。「器楽だから五線譜」みたいな短絡的な選び方ではなく、そのときの自分のやりたい音楽、ほしい音にあってると思うからあえて五線譜を選ぶというような、そういう選択の過程が常にあると。(原)
桑原:そうですね。それから、曲を頼んでくれた演奏家にもよるかもしれません。この人に演奏してもらうなら、あんまり書きすぎても…って思うときもあるので。その場合には、ちょっと書き込む情報が減ったりするかもしれない。そういう側面もあります。
海外との関わり、言葉について
———2021年に芥川也寸志サントリー作曲賞を受賞されましたが、出品に至った経緯や、受賞がその後の創作に与えた影響のようなものをお聞かせいただけますか。(小島)
桑原:芥川作曲賞については、私の作品は海外で初演されたこともあって、当初候補にカウントされていなかったようで、自分で出しました。コンクールには、大学生になってから積極的に出すようにしてましたが、それは賞が取りたかったというよりは、とにかく作品が演奏されて音になる機会がほしかったからですね。それから、コンクールを通して新しい関係が作れたり、輪が広がっていったりするので、そういう目的で出してました。
芥川作曲賞については、ノミネートされたときも全然期待してなかったんですよ。日本初演だったので、とにかく演奏がうまくいくように頑張ろうって思ってました。アンサンブル・モデルンに書いた曲だったので、要は、彼らに挑戦を持ちかけるつもりで書いた曲、そのくらい、演奏に対しての要求のレベルが高い曲で、演奏が大変なのは重々承知していました。リハーサルでは演奏者に働きかけることを一生懸命にやりました。
———やはり技術的な問題ですか。(小島)
桑原:私の作品は特殊奏法が多いので、技術面はもちろんですが、なにより「時間」を扱った曲なので、拍やテンポの扱いも難しかったと思います。でも、難しいからといってやる気をなくされてしまうと、こちらとしては非常に困るので。モチベーションをどうにか上げてもらうことを頑張りました。
———そのあたりの塩梅についてお尋ねしたいです。作曲家の理想を主張しなければいけないと同時に、あまりに言いすぎると「この曲は自分たちには無理だ」と思われてしまったりするんでしょうね。(小島)
桑原:そうなんです。指揮者もいるので、作曲家がどこまで言ってどこまで言わないかとか。「一応審査会なので、あまり個別に働きかけるのもどうなのかな」っていうのもあって。様子を伺いながら話しかけに行ってみたり、特殊奏法は演奏したことがないとイメージが湧かないので音源を聞いてもらったりとか。なにが必要かを一生懸命考えながらその場その場で対応しました。そのあたりの振る舞いも作曲家には必要なことだと思います。
———アンサンブル・モデルンなど海外の団体が演奏する場合も、リハーサルには立ち会って同じようなプロセスを経るんでしょうか?(小島)
桑原:私は海外でもなるべく立ち会うようにしていますね。再演であっても、です。コロナ前は毎月のように海外と行ったり来たりしてたんですけどね。作曲家がその場にいるといないのと全然違うと思うので。
———アンサンブル・モデルンみたいな現代音楽の専門家集団とリハーサルをやると、やはり違いますか?(小島)
桑原:一番大きいのは「こういう音が欲しいんだったら、こういう風にした方がいいんじゃない?」みたいなことを向こうから提案してもらえることですね。
———向こうの手札が豊富ってことですかね。(小島)
桑原:そうです。やりたい音のイメージにより近づけますね。音楽のやり方や捉え方、たとえばスピード感なんかが全然違う感じがします。
———日本人で他にアンサンブル・モデルンなどと仕事される方はいても、多くの場合、海外在住かと思います。桑原さんは日本を拠点にされていますが、同時に、ヨーロッパやアメリカの団体による演奏機会がすごく多いですよね。これは、大学二年生の時に「外に出なきゃ」って思ったというお話にもつながると思うんですが、どのようにして海外の演奏者や団体とコネクションを作って、キレキレの人たちと渡り合っていくのかなと。(坂本)
桑原:渡り合えているかどうかはわからないですよ(笑)。アンサンブル・モデルンについていえば、出会いは彼らがはじめて、トーキョーワンダーサイト(現トーキョーアーツアンドスペース)でアカデミーを開講したときでした。そのとき、アンサンブル ・モデルンのほぼ全メンバーが講師として来たんです。私は学部二年生でした。その時に衝撃を受けたんですよね、「すごい!」って。現代音楽の現場、ヨーロッパの第一線で活躍してる団体のすごさを目の当たりにしました。
海外への憧れもあったので、本当は「私はどこかのタイミングで留学するんだろうな」と漠然と思っていたんですけど、結局しなかったんですよね。それは能楽と出会い、その一年後には声明と出会って、日本のことをもっとちゃんと勉強しなければいけない、日本の作曲家としての基盤を持ちたいと考えたからです。それと同時に、表現の仕方、技術を本場で通用するレベルまで持っていかなければという気持ちもあって、講習会にはたくさん参加しましたね。海外のツアーとかコンペとか、できるだけ機会は逃さないようにして毎年行って、たくさん作品を出してました。太いコネクションとかは全然なく、そうした一つ一つの積み重ねです。
———ダルムシュタットの講習会にも参加されていますよね。はじめて行かれたのはいつですか?(坂本)
桑原:ダルムシュタットの講習会に全期間ちゃんと参加したのは2014年です。ただ、それ以前も、数日聴きに行くようなことは何度かしていました。2018年にはトリオ・アッカントがオランジュリーのコンサートで《In Between》を演奏したので、それにも立ち会いました。はじめて海外の講習会に参加したのは2007年のことで、数年前になくなってしまったんですけど、シュトゥットガルトでハヤ・チェルノヴィンとスティーヴン・タカスギが開催していた「シュロス・ソリテュード・サマー・アカデミー」です。その後、グラーツの「インプルス」やロワイヨモン、ルツェルン音楽祭アカデミー、アンサンブルが主催しているマスタークラスなど、いろいろと参加して、そこで頑張って曲を書いて演奏してもらいました。特にダルムシュタットは、ただ聴いているだけではあまり意味がなくて、ワークショップにたくさんアプライして、とにかく音を出してもらうこと、演奏家とどうにか交流することを意識していました。
———語学はどうやって勉強されたんですか?(坂本)
桑原:英語の日常会話ができるくらいですよ。日常会話もできてないかもしれない(笑)。2007年に最初に行ったときは流石にまずいなと思って、数ヶ月語学学校に通ったりもしましたが、あとは独学ですね。動画とか映画とか、スタンフォードの文法の教科書を勉強したりとか、そういうことを毎日継続してやると決めてやってましたね。
———論考では、日本語が持つ音やイメージから音が立ち上がる場合について書かれていましたが、海外で書く際に現地の言葉だったり、別な言語体系からインスピレーションを受けた経験はありましたか? (原)
桑原:たとえば、ディヴェルティメント・アンサンブルにイタリア語のテクストで曲を書かないといけないときとか、外国語のテクストを扱う場合には、もちろん考えますよね。海外の言葉が発端となってできた作品…あ、ベルクソンの「イマージュ」という語について考えることを目的に書いた曲はあります。ただ、やっぱりベースがわからないというのがあって、本当には理解できないなっていう感じが自分の中でどうしてもあって。
———言葉の話が出たので関連する質問をさせてください。論考では、前-言語的な声と言葉を伴った声について、両者をめぐる考察が互いに緩やかに連結するようなかたちで書かれていたかと思います。たとえば、前-言語的なものとして、猫の鳴き声は国を超えても似たようなエネルギーを持っているのに対して、言葉を伴う声であればコミュニティや文化によって違いが出てくるかと思うのですが。桑原さんのなかで、それぞれは明確に分かれているのか、それとも融合しているのか、そのあたりはいかがでしょう?(西村)
桑原:私は言葉というものは、「音」と「情報」と「かたち」で出来上がっていると思うんですね。外国語だと、その「情報」のところが理解できないんです。それがないと、理解できない微細な部分があると思います。
私は前-言語的なものを、言葉から「情報」を引いたものとして理解しています。そこにあるのは言葉の音としてのエネルギーとか、抑揚とか、身振りなわけです。
私はとくにテキストを使った作品では、素読を必ずやります。素読というのは意味を取らずに音読することです。意味がよくわからなくてもとにかく声に出してみる。そうすることによって、言葉から意味になる以前のものが立ち上がってくるんです。それが、私が「言葉以前の言葉」「前言語的なもの」というときに意味しているものです。
大伴家持の歌をテクストにしたときには『万葉集』の全4516首すべて、『古事記』の冒頭をテクストにしたときには全文を素読してからのぞむ、という具合です。すべての意味がわかるわけではないけど、そこから音像みたいなところに行き着くんです。「姿かたち」みたいなものが向こうから立ち上がってくる瞬間があるんですよね、素読を毎日続けていると。
———それは器楽作品でも似たようなことが生じるんですか? (西村)
桑原:私は「言葉以前の言葉」と音楽は、どこかで枝分かれしたんだと思っています。音楽を書くときは、その始原の状態に一度立ち戻って書きたいんです。こうした考えは、器楽曲であっても私の音の扱い方に反映されていると思いますね。
委嘱作品とこれからの展望
———2021年初演の《Nested Time》という作品についてお伺いしたいことがあります。桑原さんはいろんな曲を書かれていると思うんですけど、この曲は僕が桑原さんの作品に対して持っているイメージとはかなり異なっていてとても面白かったです。(坂本)
桑原:その曲はみんな面白いって言ってくれます、自分でも意外なんですよ。
———聞き手としても意外なところがありましたね。解説を読むと、ミニマル風であると同時に、日本の伝統音楽と繋がりがあって、「入れ子の時間」ということが書かれている。さきほど音像には身体感覚や空間性がリンクしているというお話がありましたが《Nested Time》については「ボヨーン、ボヨーン、ボヨーン」みたいな感じがしますよね(笑)。この曲のどういうところに日本の伝統音楽の影響があって、結果的にこういったミニマル風の曲が生まれたのか、お話を伺いたいです。(坂本)
桑原:日本の音楽からの影響に関しては、曲に直接的に関わるというよりは、単に私の作曲上の姿勢の問題です。「入れ子の時間」は《タイム・アビス》で扱った三つの時間のうちのひとつですね。あの曲の三つの時間は、もともと他の曲でいろいろと試していたもので、それらを一つの曲のなかで互いに行き来するやり方で扱ったらどうなるかな、という発想で書きました。
———「入れ子の時間」を使っている曲は他にどのようなものがありますか?(坂本)
桑原:たとえば古い作品だと《アラベスク》などで試していますし、《にほふ》でも使っていたかもしれない。それをきちんと定義したのが《タイム・アビス》のときだったんですね。
それはともかく、「入れ子の時間」だけにフォーカスして書いたのが《Nested Time》です。ミズーリ州国際作曲音楽祭の委嘱作品で、アラーム・ウィル・サウンドによる初演だったのですが、この団体についてはスティーヴ・ライヒの《テヒリーム》のイメージが私のなかで強くて。「いつもの私のスタイルで書いて上手に演奏してもらえるかな?」っていう不安も少しあったので、彼らの得意としている音楽に私のやり方をプラスするかたちでやった方がいいなと判断して、結果的にああいう書き方になりました。初演者についてリサーチすることも、作品を書く原動力になりますし、その辺りのサービス精神みたいなものを持ち合わせているタイプの作曲家ではあると思います。ファッションショーのランウェイのための曲だったり、調性のある曲や編曲作品だったり、実は、いつものスタイルではない曲も色々と書いていて、与えられたテーマと自分の創作との新しい関係性を見出せるのは、私の持ち味のひとつだとも考えています。
———あわせて12月に開催される「スタイル&アイデア:作曲考 第一回作品演奏会」の委嘱作品についても伺えればと思います。ヴィブラフォン・ソロのために「縦」というテーマで書いていただく作品はどうでしょうか?(原)
桑原:いろいろ試しているところなんですけど、「縦」というテーマをどうやって構成に反映させるかが難しいですね。「縦」で書こうとしても、必ず「横」の繋がりって必要になっちゃうんですよね、音楽って。その横の繋がりをどうやって断ち切ろうかっていうのが課題になってます。なるべく、自分が普段から持っている「横」の感覚から離れるにはどうしたらいいだろう、というのを考えています。
———とても楽しみにしています。最後に、これからの創作の展望というか、現在関心を持たれていることなどについてお話しいただけますか?論考の最後には、時間構造の問題に関心がシフトしつつある、というような記述もありましたが。(原)
桑原:私は仏事の時間がとても好きで、長い時間ずっと聴いていられるんですけど、法会全体のなかにいくつもの経文が配置されて、それぞれがちゃんと役割を課せられていて時間を作っていくその無駄のなさや、そこに没入することで日常と違う時間性に自分の身体がリセットされる感じ、そういったものにすごく興味があります。そういうところから時間の構築の仕方を得られないかなって思っていますね。
———その仏事というのは?(原)
桑原:要は、お寺で行われる法要ですね。それぞれのお経に語られる内容と意味があって、その配置や構成にも意味があるんです。
———それは複数の異なるお経が同時に読まれるんですか?(原)
桑原:あんまりそういうことはないですね。秘曲とかの場合には、わざと被せて、みたいな場合もありますけど。興味を惹かれるのは法要全体の形式です。たとえば、東大寺の修二会は二週間に渡って行われるんですけど、最初の一週間と次の一週間で意味が違うし、一日ごとに意味があることに加え、その一日が「六時」に分かれてて、といったように。全体としての形式となかを覗いた時の形式、細部と全体とが相互に機能して、まさに曼荼羅的な構造が出来上がっているんです。そういうところから音楽の構成の仕方を自分なりに考えられないかと思っています。
———お寺は頻繁に行かれるんですか?(西村)
桑原:よく行きますね。声明作品を演奏してくださっている真言宗豊山派と天台宗のお坊さん方がお稽古する時や法要の時、それ以外にもリサーチを兼ねて行ったりします。東大寺の修二会も奈良まで行って、今年は、二週間のうちのこの日って決めて、二月堂の裏で夕方の「初夜」から聴きはじめ、深夜二時ごろに「晨朝」まで終わって宿に戻り、翌日午後にまた「日中」から聞いて、みたいな風にして。
法要以外にも、たとえば神社の奉納の演奏とか、神楽、各地の伝統的なお祭りなどなんかにも興味があって聞きに行ったりしています。やっぱりそこに行ってみないとわからないことがたくさんあるので、地方にも足を運んでます。富山県の「おわら風の盆」など、すごく美しかったです。そういうのを夜通し聞いてるんですよね。
———土地によって全く違うから実際に行ってみないとわからないですよね。(西村)
桑原:それぞれ全部違います。ルーツが一緒で、似ているものもありますけど。とくに山を隔てていたりすると違うんですよね。長野の「新野の盆踊り」もすごく面白いですよ。太鼓や笛が入っていない、歌だけで舞う盆踊りで、歌も舞も美しいのですが、四日間やって最後の日に大団円を迎える、といったようにやはり構成も面白いです。同じ場所で、冬は「雪祭り」が行われるのですが、大雪のなかを夜中から朝の七時ぐらいまで、火の前で温まりながら過ごしたりとか。結構サバイバルですね(笑)。
———海外遠征にしろ、そうしたリサーチにしろ、誠実な活動があって、そのうえに桑原さんの作品が成り立っているんだなということがよくわかりました。(小島)
桑原:「とりあえずやる」「やれることはやらなきゃ」っていうだけの話です。あとは、なんにせよ、自分で体験して実感してみないと。自分でちゃんと経験したいなっていう気持ちですね。
2023年10月18日
Zoomにて
インタビュアー:小島、坂本、西村、原